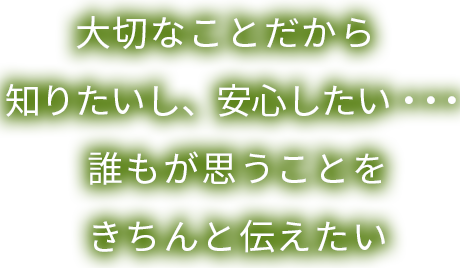
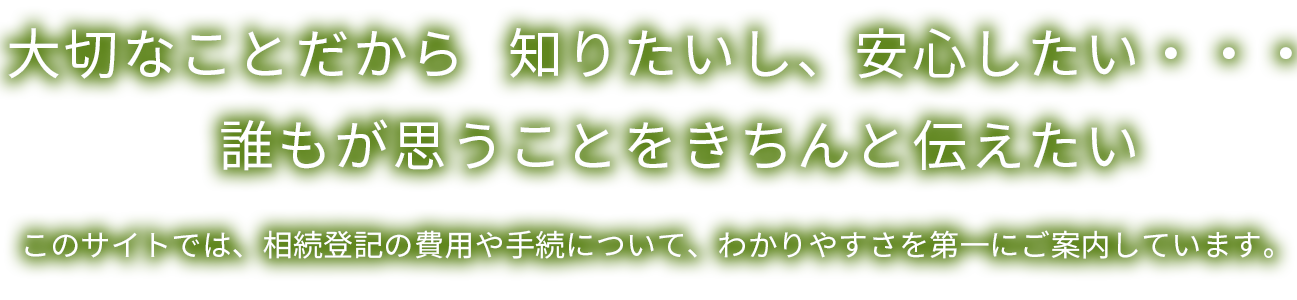
司法書士おだ事務所 司法書士
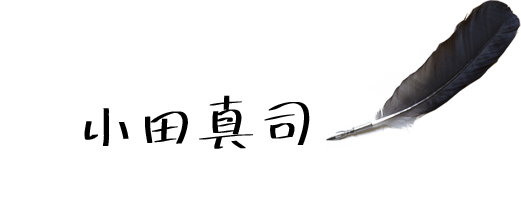
相続登記の義務化についてはメディアで取り上げられることも増えたのでご存知のかたが多いかもしれません。
❖❖❖❖❖❖
いきなり「義務化する」と言われても、相続登記は故人がのこした財産をどのように引き継ぐかを決めたあと、それを記録に残すための最後のステップなので、相続登記だけを簡単に済ませるのは難しいですし、法的なリスクの観点からもおすすめできません。
❖❖❖❖❖
しかし、いざ専門家に相談しようと思っても、費用がどのくらいかかるのか分からなければ、相談するのを身構えてしまうのではないでしょうか。
❖❖❖❖
このサイトでは、司法書士の報酬を含む相続登記にかかるおおまかな費用を、いくつかの質問に答えるだけで簡単にシミュレーションすることができます。
❖❖❖
また、相談をご希望されるときは、カレンダー予約で簡単にオンライン相談(無料)をご予約いただくこともできます。
相談は基本的にオンラインでおこないますので、お住まいの地域を問わずに対応できますし、非対面のため安心してご相談いただくことができます。
❖❖
また、相続について皆さんに知っておいてほしい基本的なことがらを、分かりやすく解説したコンテンツもあるので、そちらも是非ご覧ください。
❖
相続登記をしないままにしておくと、故人がのこした土地や建物が財産的な価値を失ってしまうこともあります。
このサイトが生前に故人が築き上げた財産を守り、ご家族によって確実に将来に受け継いでいくお役に立てば幸いです。
相続登記の義務化とは
相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度などについて、かいつまんで解説します。
詳しい内容はコラムで随時更新しますので、そちらをご覧ください。
その原因のひとつが、相続登記がされていないことです。
相続登記がされないままの土地や建物は、誰が所有者か分からない状態にあるため、売却することはもちろん、適切に管理することも困難です。
これによる莫大な社会的コストを削減するため、土地や建物を相続したら必ず相続登記をしなければならないものとされました。
しかし、所有者が亡くなったのが令和6年4月1日よりも前か後かにかかわらず、相続登記の義務化の対象になります。
そのため、所有者が令和6年4月以降に亡くなった場合はもちろん、それ以前、たとえば平成や昭和、さらにはそれ以前に亡くなっているような場合でも、制度開始後すみやかに相続登記をする必要があります。
相続登記をせずに放置しておくと10万円以下の過料という罰則が科せられる可能性があります。
なお、過料は、行政的なペナルティなので、いわゆる前科になることはありません。
所有者が亡くなったからといって、すぐに相続登記をすることができるとは限りません。
そのような場合には相続人がペナルティを受けることがないような仕組みになっています。
たとえば次のようなケースは、義務化の対象にはならないとされています。
①相続人が重病を患っているケース
②数次にわたって相続が発生し、相続人が多数に上るケース
③相続人のあいだで遺産について争いがあるケース
相続人のあいだで争いがあるわけではないのに、一部の相続人が話し合いを先延ばしにしているだけのケースなどは義務化の対象になります。それでは、早く話し合いをしたいと思っている相続人はペナルティを受けなければならないのでしょうか?
このような場合には、相続人申告登記という制度を利用することができます。
これは、相続登記よりも簡易に、名義人が亡くなったこと、そして自分が相続人であることを法務局に申告して登記簿に記載してもらう仕組みです。
相続人申告登記をすれば、相続登記の義務を果たしたものとして扱われるため、ペナルティを受けることはありません。
将来的には住民基本台帳ネットワークシステムと法務局のシステムを接続して、所有者の関与なしに住所変更登記をする構想もあるようですが、当面のあいだは所有者が住所を変更するたびに住所変更登記をする必要があります。
所有者不明土地の発生を防ぐため、相続した土地を国に引きとってもらう制度も始まりました。
相続した土地を手放したいと考えている方は少なくありません。
資産価値のある土地であれば売却することもできますが、そうでない土地のほうが多いのが現実です。
そのような土地が放置されると、管理が行き届かずに荒廃してしまい、住宅地の場合は近隣の迷惑にな
ったり、山林の場合は山崩れなど自然災害の原因になったりすることもあります。
そこで、このような事態がおきないようにするため、一定の要件をみたす場合には、相続した土地を国に引き取ってもらうことができるようになりました。
ただし、建物が建っている土地や道路として使われている土地など制度の対象にならないものがあるので注意が必要です。
まず、所有者不明の土地や建物を適切に管理し、必要があれば処分するための制度ができました。
たとえば、買いたい土地があるが相続登記がされていないために所有者が分からない場合でも、その土地だけを管理する管理人を裁判所に決めてもらい、その人から土地を購入することが可能です。
次に、所有者が誰か分かっているが適切に管理されていない土地や建物についても同様の制度ができました。
たとえば、隣の空き家が放置されていて崩れてきそうな場合には、その建物だけを管理する管理人を裁判所に決めてもらい、修繕したりごみを撤去したりすることができます。
ただし、所有者が誰か分かっているため、建物を取り壊すなど処分するためには、所有者の同意が必要です。
→こちら
法務局から相続登記の通知が届いた方へ
令和4年10月3日から、各地の法務局が土地や建物を相続した方に「長期間相続登記等がされていないことの通知」という手紙を送っています。
法務局のような公的機関からの手紙を受け取っても、最近はさまざまな方法で人をだまそうとする悪い人がいるので、不審に思われる方も多いかもしれません。
不安な方は、法務局が公開しているサンプルがあるので、まずはこちらを確認してください。
➤ 「長期間相続登記等がされていないことの通知」(サンプル)/福岡法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/content/
001382692.pdf
次に、「通知」に記載されている法務局の連絡先が本物と同じかどうか確認してください。
全国の法務局の連絡先は、管轄一覧から調べることができます。
➤ 管轄一覧から探す/管轄のご案内/法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
kankatsu_index.html
送られてきた「通知」の連絡先と管轄一覧の連絡先が同じなら本物と考えて良いでしょう。
とくに、この通知が届いたということは、本来なら個人で行わなければならない相続関係の調査をあらかじめ国が行ってくれているということなので、手続を進めやすくなっています。
通知から時間がたってしまうと、さらに相続が発生するなどして関係が複雑になるため、できるだけ早めの対応が重要になります。
なお、長期間相続登記がされていないことから、相続登記の義務化の例外②(数次にわたって相続が発生)に該当する可能性もありますが、そうではないケースも数多くみられるので、放置しておくとペナルティを受けるおそれがあります。
ご心配な方は、司法書士にご相談ください。
これは土地の所有者から現在の相続人までを家系図のようなかたちで一覧にしたものです。
通知に記載された法務局に限らず、全国どこの法務局でも発行してもらえますし、郵送で発行してもらうことも可能です。
発行の手続は、次の法務省のホームページに掲載されています。
➤ 長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ/法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00470.html 次に、法定相続人の皆さんのうち誰が土地を相続するか話し合っていただきます。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員が話し合いの内容に同意しなければ成立しないので注意が必要です。
たとえば、法定相続人情報に記載された相続人は、国が相続関係を調査した時点のものなので、通知を受け取った時点ですでに亡くなっている方がいるかもしれません。
その場合は、亡くなった方の相続人を調査したうえで、その相続人を含めて遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議が成立したら、協議の内容にしたがって、相続登記を申請します。
遺産分割協議など、相続に関するきまりごとについては、相続についてのほか、コラムでも分かりやすく解説しているので、こちらをご覧ください。
昔は子供が10人近くいる家庭が多かったことを考えると、相続人が総勢数十名になっていることも十分ありえます。
当然、会ったこともなければ、名前を聞いたこともない親戚がほとんどでしょうから、そういった方と遺産分割協議をすることが手続を進めるうえで一番むずかしいことかもしれません。
そうかといって放置しておくとペナルティのおそれがありますし、なによりも放置しておくと相続人が増え続けてしまうので、国が相続関係を調査してくれた今こそ相続登記をするのに最適なタイミングです。
この点、司法書士にご依頼いただけば、他の相続人への連絡は司法書士が行い、皆さんのご意向にそって手続を進めますので、相続人の皆さんのご負担を軽くできるのではないかと思います。
義務化の対象
令和5年以降に不動産の名義人が亡くなったときは、相続登記の義務化の対象となります。この場合、相続人は3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、それ以前に亡くなった方の不動産についても義務化されるため、令和5年から3年以内をめどに相続登記をする必要があります。
亡くなってから時間がたつと相続関係が複雑化し、手続が難しくなってしまいますので、亡くなった時期にかかわらず、早めの相続登記をおすすめします。
相続登記しないとどうなる
※過料と似たペナルティとして「罰金」があります。罰金は前科になってしまいますが、「過料」ではそのようなことはありません。これは、前者が刑事責任を問うものなのに対して、後者が行政手続上の責任を問うものであるという違いによるものです。
注意が必要なこと
この通知は、名義人が亡くなってから数十年たってから送られてくるため、現在の相続人までの間に3世代以上あいていることも珍しくありません。
昔は子供が10人近くいることも珍しくなかったことを考えると、現在の相続人が総勢数十名になっていることも十分ありうることです。
当然、会ったことも名前を聞いたこともない親戚がほとんどでしょうから、そういった方と遺産分割協議をすることが一番のネックになります。
このような土地の相続登記も相続登記義務化の対象になりますし、なにより放置しておくと相続人は増え続けるので、相続人調査を国がしてくれた今のタイミングで相続登記をしておくことを強くお勧めします。
ご依頼いただけば、司法書士から他の相続人にご連絡しますので、ご自身で連絡していただく必要はありません。

