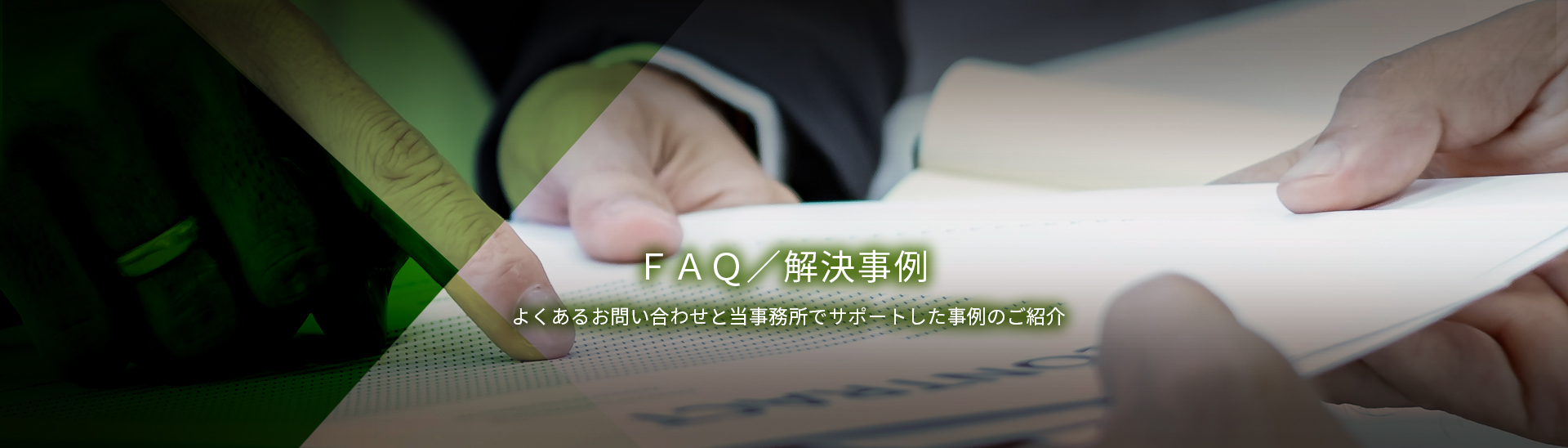
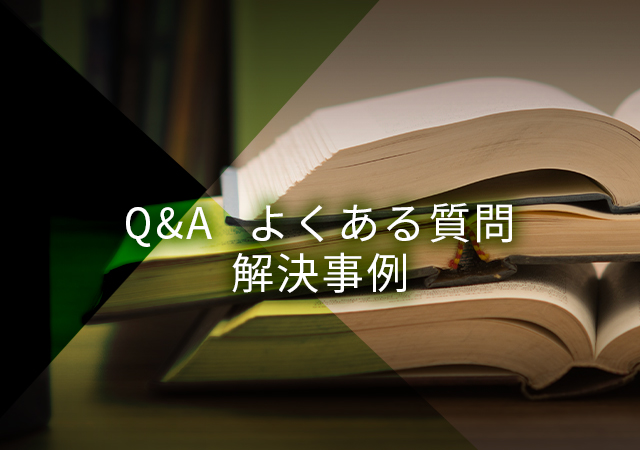
費用について
初回相談は無料です。2回目以降のご相談は30分につき2,200円(税込)となります。
当事務所の実績にもとづく平均的な費用を表示しているため、前後することがあります。 お見積金額を上回ることもありますが、比較的難しいケースを含めて平均をとっているので、表示された金額を下回ることも少なくありません 。
かんたん見積りは典型的なケースにしか対応していないため、手続が難しいケース、たとえば、何度も相続が発生しているようなケース、相続人が外国にいるケース、相続人の行方が分からないケース、ご入力いただいた固定資産税評価額が実際の評価額を大きく超えるようなケースでは、費用が表示された金額を超えることがあります。
ご依頼いただく際に着手金として2万円を振り込んでいただきます。着手金は、相続関係の調査の実費の支払いにあてます。相続関係の調査が終わりましたら御見積書をお送りしますので、内容をご確認ください。費用のお支払いはお見積り後、申請までの間にお願いしております。
解約のタイミングによって次のようになります。
相続関係の調査に着手する前に解約されるときは、お預かりした着手金を全額お返しいたします(振込手数料はご負担いただいております。)。
調査に着手した後は支出した実費とすでに行った業務分の報酬を差し引いて、残額をお返しいたします。
詳しくは、ご依頼いただく前に解約ポリシーをご提示しますので、そちらをご確認ください。
手続について
相続のパターンは多種多様なため、30分の相談時間で具体的な手順をお伝えすることはできません。各地の法務局がご自分で手続される方のための相談窓口を設けているので、そちらにお問い合せ下さい。
手続に必要な書類の準備は、印鑑証明書など一部を除き、司法書士が行います。相続人の皆さんには遺産の分け方を決めていただき、その内容をもとに司法書士が作成した書類に署名捺印していただきます。そのあとは司法書士が法務局に提出する書類を作成して、相続登記を申請しますので、完了までお待ちください。
相談について
予約画面で相談を希望する日時を選択し、予約フォームに必要事項を入力して送信してください。
受付完了のメールが自動で送信されます。
翌営業日から3日以内にオンライン相談の招待状(URLなどのログイン情報)をメールでお送りします。
予約した日時になりましたら、招待状に表示されたURLからオンライン会議室にアクセスしてください。
司法書士がお話をおききします。
ご記入いただいた「相続チェックシート(※リンク)と、運転免許証(または運転経歴証明書、マイナンバーカードなどの顔写真付き公的証明書)をご用意ください。
また、次のものがお手元にあればご用意ください(なくても問題ありません)。
・土地建物の権利証(または登記簿謄本)
・土地建物の固定資産税納税通知書(または名寄帳、固定資産税課税台帳)
・故人の戸籍謄本と住民票
・故人の遺言書(封がされている遺言書は開封しないでください)。
そんなことはありません。相談終了後に落ち着いて依頼するかどうかゆっくりご検討ください。
メールでご連絡ください。
その際、オンライン相談の招待をお送りしたメールに返信するか、件名にオンライン相談の日付を記載して新規メールを送信してください。
運転免許証などに記載された住所に書類をお送りするので、必要事項をご記入のうえ返信用封筒で当事務所にお送りください。
お送りする書類のなかに着手金のご案内がありますので、そちらをご確認のうえ着手金をお振込みください。
書類の返送と着手金の振込みが完了しましたら、相続関係の調査にはいります。
解決事例
遠方にある土地建物を相続した方からのご依頼で、土地建物の所在地の法務局に相続登記をオンライン申請し、戸籍謄本などの書類は法務局に郵送することによって相続登記を完了した。 遠方にある土地建物の相続登記はよくご依頼いただきます。
相続人のなかに遠方に居住している方がいるため、司法書士から手紙などで相続についての意向を確認したところ全員の合意がまとまったので、相続登記を完了した。
このように、他の相続人が遠方にお住いの場合でも手続を進めることは可能です。
子供がいない夫婦のご主人からの相談で、自分の死後に相続人になる妻と兄弟がもめるのは避けたいという要望にしたがって遺言を作成し、ご本人が亡くなったのちにこの遺言によって奥様への相続登記を完了した。 遺言がなければ配偶者と兄弟姉妹の全員の合意で誰が相続するかを決めなければなりませんが、このように適切な遺言をのこしておけば、兄弟の関与なしに相続登記をすることができます。
子供は自分ひとりだと思っていたが、戸籍調査をしたところ父が一度離婚しており、離婚前に生まれた子供がいることが分かった。司法書士からその方に連絡して登記手続に協力してもらい、相続登記を完了した。 このほかにも、祖父名義の土地の相続で祖父が養子をとっていたケースのように、親族が誰も知らない相続人が現れることがあるので、相続人調査が重要となります。
兄弟姉妹間の相続で戸籍調査をしたところ、名前も聞いたことがない異母兄弟がおり、戸籍上生存していることが分かった。 追跡調査したところ、その異母兄弟が実際は死亡している可能性が高いことが判明したため、家庭裁判所の手続(失踪宣告)により異母兄弟を遺産分割の当事者から除外し、無事に相続登記を完了した。 なお、ケースによっては当事者から除外できないこともあります。その場合は、連絡が取れない相続人のための財産管理人を裁判所で選任してもらうことになります。
相続した実家を売却して金銭で分配したいという要望があり、これに適した遺産分割の方法を提案して相続登記を完了。その後売却が決まり、この内容にしたがって金銭を分配した。 売却を前提に相続登記をする場合は、税金や翌年の健康保険料などへの影響もあるので、慎重に手続を進める必要があります。
