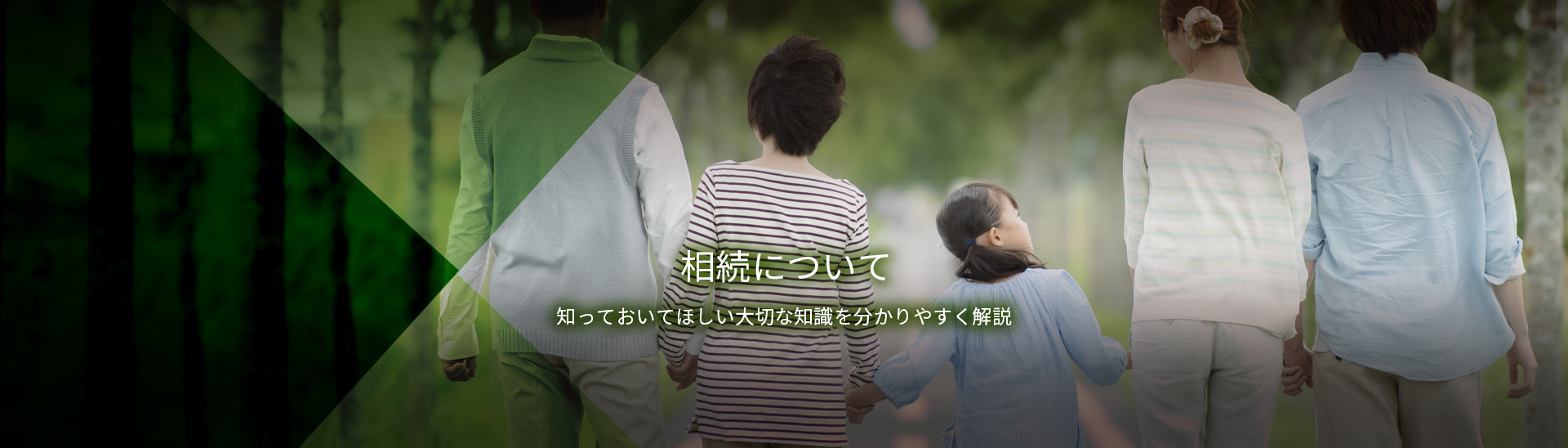

01
遺言
遺言とは ❖❖❖❖
遺言は、自分の財産をどのように残すかを決める方法です。
エンディングノートとは異なり、法的な効力があります。
エンディングノートとは異なり、法的な効力があります。
遺言の効果 ❖❖❖❖
遺言がないと相続人全員で分け方を話し合わなければなりません。
遺言があればそこに書かれたとおりに財産の行き先が決まるため、話し合いは必要ありません。
たとえば子供のいない夫婦は、それぞれの兄弟姉妹も相続人になります。
そのため、兄弟姉妹を含めて話し合いをしなければなりません。
この点、遺言を作成しておけば兄弟姉妹の関与なしにご自宅などの財産をお互いに残すことができます。
また、相続人以外の方に財産を譲りたいときにも便利に利用することができます。
遺言があればそこに書かれたとおりに財産の行き先が決まるため、話し合いは必要ありません。
たとえば子供のいない夫婦は、それぞれの兄弟姉妹も相続人になります。
そのため、兄弟姉妹を含めて話し合いをしなければなりません。
この点、遺言を作成しておけば兄弟姉妹の関与なしにご自宅などの財産をお互いに残すことができます。
また、相続人以外の方に財産を譲りたいときにも便利に利用することができます。
遺言の種類 ❖❖❖❖
よく使われる遺言として、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」があります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人がご本人からヒアリングしながら作成する遺言です。
専門家が作成するため安心して財産をのこせる反面、作成してもらうための費用がかかります。
自筆証書遺言は、ご本人が手書きで作成する遺言です。
ご自分で作成するため費用がかからない反面、作成する際にミスがあると法的な効力が認められないので注意が必要です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人がご本人からヒアリングしながら作成する遺言です。
専門家が作成するため安心して財産をのこせる反面、作成してもらうための費用がかかります。
自筆証書遺言は、ご本人が手書きで作成する遺言です。
ご自分で作成するため費用がかからない反面、作成する際にミスがあると法的な効力が認められないので注意が必要です。
遺留分 ❖❖❖❖
親子や夫婦は、お互い経済的に支えあって生活しているのが普通です。
そのため、たとえば夫が亡くなった場合にすべての財産を妻や子供以外のだれかに譲るという遺言があったらどうでしょうか。
のこされた家族の生活がたちゆかなくなるかもしれません。
そこで、これらの方々にある程度の財産がのこるような制度があります。
これが遺留分と呼ばれるものです。
遺言を作成するときにはご自分が亡くなったあとにトラブルの種をのこさないよう、遺留分にご注意ください。
そのため、たとえば夫が亡くなった場合にすべての財産を妻や子供以外のだれかに譲るという遺言があったらどうでしょうか。
のこされた家族の生活がたちゆかなくなるかもしれません。
そこで、これらの方々にある程度の財産がのこるような制度があります。
これが遺留分と呼ばれるものです。
遺言を作成するときにはご自分が亡くなったあとにトラブルの種をのこさないよう、遺留分にご注意ください。
02
法定相続
法定相続とは ❖❖❖❖❖
遺言がないときに、のこされた財産を誰がどのくらい相続するのでしょうか。
これについては、法律で決められています。 これが法定相続です。
これについては、法律で決められています。 これが法定相続です。
誰が相続するか ❖❖❖❖❖
夫が先に亡くなると妻が、妻が先に亡くなると夫が、それぞれ相続人になります。
そのほかに、子供がいれば子供が、子供がいなければ両親が、すでに両親も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。
そのほかに、子供がいれば子供が、子供がいなければ両親が、すでに両親も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。
わかる範囲で構いませんので、記入して相続関係を明確にしましょう
相続する割合 ❖❖❖❖❖
相続人が一人だけの時は全ての財産をその方が相続します。
相続人が何人かいるときは、一定の割合で分け合うことになります。
これを法定相続分といいます。
法定相続分は相続のパターンによつて次のように変わります。
相続人が何人かいるときは、一定の割合で分け合うことになります。
これを法定相続分といいます。
法定相続分は相続のパターンによつて次のように変わります。
| 配偶者と子供が相続人のとき | 配偶者 1/2 子供 1/2 |
|---|---|
| 配偶者と両親が相続人のとき | 配偶者 2/3 両親 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
何を相続するか ❖❖❖❖❖
法定相続分は、残された財産の全体に対する割合にすぎません。
そのため、具体的にどの財産を誰がどのくらい相続するかは話し合いで決める必要 があります。
これを遺産分割協議といいます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に場所を移して話し合いをすすめること になります。
これが遺産分割調停や遺産分割審判と呼ばれる手続です。
そのため、具体的にどの財産を誰がどのくらい相続するかは話し合いで決める必要 があります。
これを遺産分割協議といいます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に場所を移して話し合いをすすめること になります。
これが遺産分割調停や遺産分割審判と呼ばれる手続です。
相続できない人 ❖❖❖❖❖
❖❖相続人廃除
たとえば、父親が息子からひどく虐待されたことがあり、その人に財産を残さないという意思を明確にしたときは、その人は父親の財産を相続することができません。
これを「相続人廃除」といいます。
この意思は、ご本人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言に記載する方法によって示す必要があります。
❖❖相続欠格
たとえば、相続人の誰かが故人を殺害しようとしたり、故人の遺言書を隠したり捨てたりした場合は、その人は故人の財産を相続することができません。
これを「相続欠格」と言います。
相続欠格は、相続人廃除とは異なり、故人の意思にかかわらず法律によって相続人の資 格を失わせる制度です。
たとえば、父親が息子からひどく虐待されたことがあり、その人に財産を残さないという意思を明確にしたときは、その人は父親の財産を相続することができません。
これを「相続人廃除」といいます。
この意思は、ご本人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言に記載する方法によって示す必要があります。
❖❖相続欠格
たとえば、相続人の誰かが故人を殺害しようとしたり、故人の遺言書を隠したり捨てたりした場合は、その人は故人の財産を相続することができません。
これを「相続欠格」と言います。
相続欠格は、相続人廃除とは異なり、故人の意思にかかわらず法律によって相続人の資 格を失わせる制度です。
03
相続登記について
相続関係の調査 ❖❖❖❖
誰が亡くなって、どのような不動産をのこしたのか。
また、亡くなった方の相続人は誰かを調査します。
調査は、戸籍謄本や課税台帳を取り寄せることによって行います。
また、亡くなった方の相続人は誰かを調査します。
調査は、戸籍謄本や課税台帳を取り寄せることによって行います。
相続人の話し合い ❖❖❖❖
遺産分割協議をして、のこされた不動産を誰が引き継ぐのかを話し合います。
話し合いがまとまったら、その結果を書面にします。
これを遺産分割協議書といいます。
なお、遺言があれば、故人の遺志にしたがつて財産の行き先が決まります。
話し合いがまとまったら、その結果を書面にします。
これを遺産分割協議書といいます。
なお、遺言があれば、故人の遺志にしたがつて財産の行き先が決まります。
相続登記の申請 ❖❖❖❖
法務局に相続登記を申講します。
申請するときは、戸籍謄本や遺産分割協議書などを提出します。
また、法務局の手数料もこの時に納付します。
申請後は、法務局の審査が終わるのを待ちます。
申請するときは、戸籍謄本や遺産分割協議書などを提出します。
また、法務局の手数料もこの時に納付します。
申請後は、法務局の審査が終わるのを待ちます。
相続登記の完了 ❖❖❖❖
審査の結果、問題がなければ登記簿が書き換えられます。
その後、新しい権利証が発行され、相続登記が完了します。
提出した戸籍謄本等の書類は、手続をふめば返却してもらえます。
その後、新しい権利証が発行され、相続登記が完了します。
提出した戸籍謄本等の書類は、手続をふめば返却してもらえます。
04
相続しない選択
相続放棄とは ❖❖❖
相続人は借金などのマイナスの財産も相続します。
負債が多いようなときは、相続しないという選択も可能です。
この期間を過ぎると、相続放棄が難しくなるのでご注意ください。
負債が多いようなときは、相続しないという選択も可能です。
この期間を過ぎると、相続放棄が難しくなるのでご注意ください。
相続放棄の手続 ❖❖❖
相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続する必要があります。
この手続には、相続開始後 3か月という期間制限があります。
この手続には、相続開始後 3か月という期間制限があります。
相続放棄の効果 ❖❖❖
相続放棄は「相続人であることをやめる」制度です。
そのため、一度相続放棄するとプラスの財産も相続することができません。
また、たとえば子供全員が相続放棄するとどうなるでしょうか。
この場合、相続人としての子供はいなかったことになります。
代わりに故人の両親や兄弟姉妹が相続人として登場するため、遺産を分けるためにはこの方々と話し合いをしなければなりません。
このように予期しない結果になることもあるので注意してください。
そのため、一度相続放棄するとプラスの財産も相続することができません。
また、たとえば子供全員が相続放棄するとどうなるでしょうか。
この場合、相続人としての子供はいなかったことになります。
代わりに故人の両親や兄弟姉妹が相続人として登場するため、遺産を分けるためにはこの方々と話し合いをしなければなりません。
このように予期しない結果になることもあるので注意してください。
